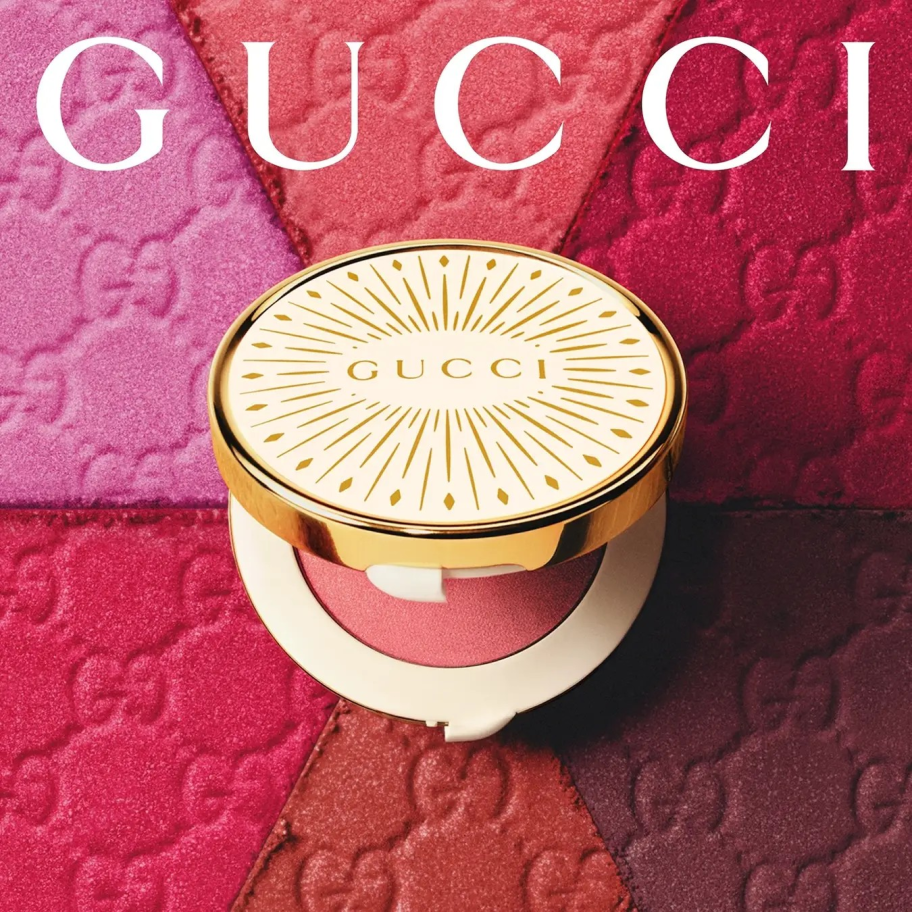「おなかの調子を崩しやすい」「繰り返す腹痛が多く、原因がよくわからない」……と悩んでいませんか?
繰り返される原因不明の腹痛は、「過敏性腸症候群」かもしれません。今回は、過敏性腸症候群とはどんな病気なのか、そして治療に用いられるプロバイオティクスや漢方薬についてご紹介します。
過敏性腸症候群はどんな病気?
過敏性腸症候群とは、消化器疾患がないのにおなかの調子が悪く、慢性的に症状を繰り返してしまう病気のことです。
過敏性腸症候群の原因は、心身のストレスや自律神経の乱れといわれています。まずは、過敏性腸症候群のタイプ別の特徴と、診断基準をみていきましょう。
女性は便秘型が多い
過敏性腸症候群には主に「下痢型」「便秘型」「混合型」の3つのタイプがあります。
下痢型は、急な便意と激しい下痢症状があらわれるタイプです。水っぽく粘液のような便が出る特徴があります。
便秘型は、便がうさぎの糞のようにコロコロとした水分のない状態になり、慢性的な便秘を繰り返すタイプ。腹痛やおなかの張りを感じることもあります。
混合型は、下痢と便秘を繰り返すタイプです。とくに、ストレスによって腸の状態が乱れます。
性別でみると、男性は比較的下痢型が多く、女性は便秘型や混合型が多い傾向にあるといわれています(※1)。
過敏性腸症候群の診断チェック
過敏性腸症候群の診断には、「RomeⅣ基準」といわれる国際的な基準を使用するのが一般的です。
<RomeⅣ基準>
直近3か月で週1日以上、腹痛が繰り返し起こり、次の項目に2つ以上当てはまる。
・症状と排便が関連している
・腹痛が排便頻度の変化を伴う
・腹痛が便の形状の変化を伴う
また、6か月以上前から過敏性腸症候群の自覚症状があること、直近3か月で上記の項目を満たすことも判断基準になります(※2)。
過敏性腸症候群に有効な「プロバイオティクス」とは?
過敏性腸症候群の治療法のひとつに「プロバイオティクス」があります。プロバイオティクスとは、腸内細菌のバランスを改善する有益な微生物のことで、乳酸菌やビフィズス菌などが有名です。プロバイオティクスを含む食品の摂取は、日本消化器病学会でも強く推奨されています。
<プロバイオティクスを含む食品の一例>
・ヨーグルト
・納豆
・ぬか漬け
・キムチ
・味噌
・塩麹
プロバイオティクスは乳製品や発酵食品にとくに多く含まれているので、普段の食卓に意識的にとり入れてみましょう。
過敏性腸症候群に用いられる3つの漢方薬
プロバイオティクスのほかに、根本改善を目指す漢方薬も過敏性腸症候群の治療に使用されることがあります。臨床試験の結果はまだ少ないものの、漢方薬の一部の有効性が日本消化器病学会ガイドラインでも認められているのです(※3)。
ここからは、過敏性腸症候群に用いられる漢方薬を3つご紹介します。
桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)
桂枝加芍薬湯は、排便が困難で、おなかの張りや痛みを感じる方に向いた漢方薬です。過敏性腸症候群の患者に対して行われた実験では、腹痛改善傾向がみられ、タイプ別では下痢型に有意な改善が認められた結果があります。
半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
半夏瀉心湯は、腸を温めることで下痢や軟便の症状を和らげる漢方薬です。過敏性腸症候群では下痢型の症状への効果が報告されていて、腹痛や便の形状への効果がみられ、大腸内の水分吸収を促進させる効果もみられます。
大建中湯(だいけんちゅうとう)
大建中湯は、おなかが張り、腸内にガスがたまりやすい方に向いている漢方薬です。過敏性腸症候群では便秘型のタイプに有効性が示唆されていて、腹部の膨満感や残便感、おならなどに有意な改善がみられました。
漢方薬を使うときはプロに相談してみよう
漢方薬は、植物や鉱物といった自然由来の生薬で作られており、一般的に西洋薬よりも副作用リスクが低いといわれます。また、飲むだけで済むので、生活習慣を大幅に変更することもなく、続けやすい点もメリットです。
ただし、漢方薬を使う場合は、それぞれの症状に見合った漢方薬の選択や、漢方薬と体質との相性も重視する必要があります。体質に合っていない漢方薬を使用しても本来の効果は期待できません。
漢方薬を使うときは、漢方に精通した医師や薬剤師に相談し、適切な漢方薬を提案してもらいましょう。
最近は、オンラインの「あんしん漢方」というサービスも人気です。あんしん漢方は体質診断、漢方薬の提案、アフターフォローに至るまですべてネットで完結するので、通院する時間がない方にもおすすめ。心配なときはいつでもプロに相談できる点も、従来のサービスとは異なるメリットがあります。
まずは規則正しい生活習慣で予防・改善
過敏性腸症候群にはプロバイオティクスや漢方薬の活用が有効ですが、まずは規則正しい生活を送り、心身をしっかり休めることもとても大切です。しっかりと生活習慣を整え、過敏性腸症候群を予防、改善していきましょう。
<参考文献>
(※1)一般社団法人 日本大腸肛門病学会 過敏性腸症候群について|市民のみなさまへ
(※2)(※3)日本消化器病学会ガイドライン 過敏性腸症候群(IBS)
<この記事の監修者>
あんしん漢方薬剤師
中田 早苗(なかだ さなえ)
デトックス体質改善・腸活・膣ケアサポート薬剤師・認定運動支援薬剤師。病院薬剤師を経て漢方薬局にて従事。症状を根本改善するための漢方の啓発やアドバイスを行う。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でも薬剤師としてサポートを行う。
●あんしん漢方(オンラインAI漢方):https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=211231g6sdf10024&utm_source=shindere&utm_medium=referral&utm_campaign=250422