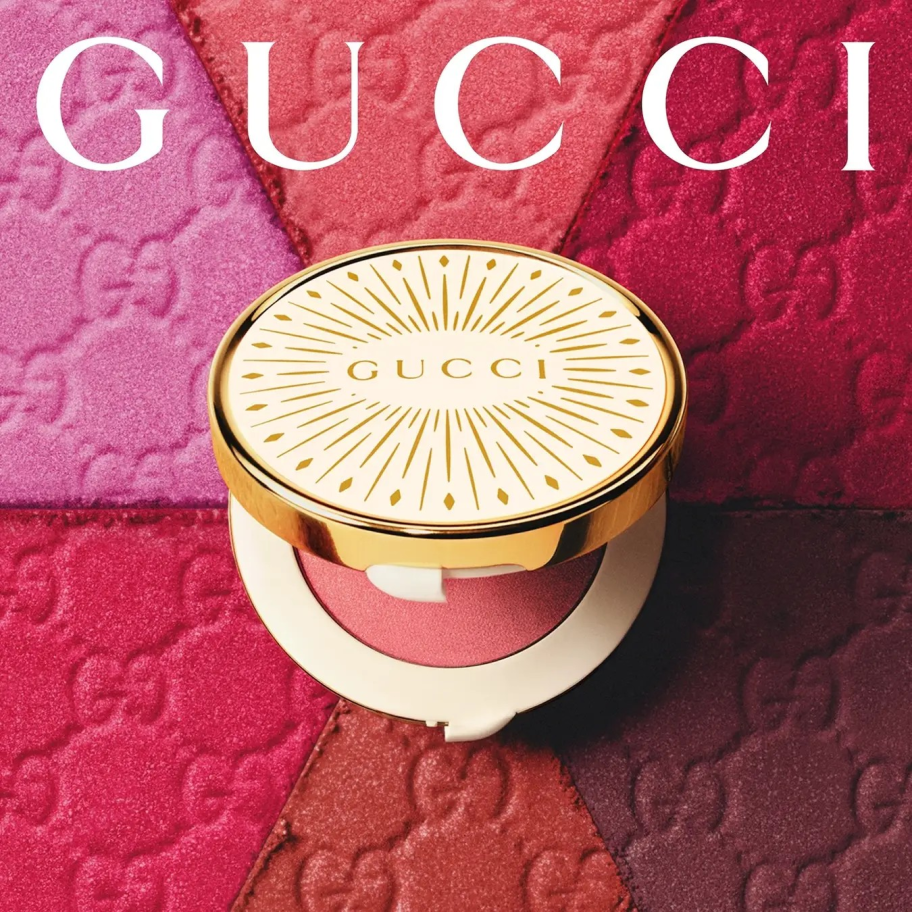新生活が始まり、緊張感のなかで一生懸命がんばってきたけれど、5月に入ってから「なんとなく元気が出ない」「朝起きるのがつらい」と感じていませんか?
もしかすると、それは5月病のサインかもしれません。
5月病は、真面目な人ほどかかりやすいとされており、放置するとうつ病などの深刻なメンタル不調につながることも。
今回の記事では、5月病を正しく知り、悪化させないための対処法をご紹介します。
その不調、5月病かも?
「5月病」は正式な医学用語ではありませんが、5月に起こりやすいため、通称として使われています。
医学的には「適応障害」に分類され、ストレスにうまく対応できず、心身にさまざまな症状があらわれるのが特徴です。
とくに4月に入社・異動・進学・引っ越しなど環境の変化があってストレスを感じていた人が症状を感じることが多く、GW明けごろから気分の落ち込みや倦怠感、意欲の低下が続くケースがあります。
早めに自分の状態に気づき、適切なケアをすることが、深刻なメンタル不調を防ぐ第一歩になります。
5月病チェックリスト
自分は大丈夫だと思っていても、もしかすると、気づかないうちに5月病になっていたり、その一歩手前になっていたりするかもしれません。
まずは、下のチェックリストで今の自分の状態を振り返ってみましょう。
・夜はなかなか寝付けず、 朝も起きられない
・洋服を選べない、出かける準備が進まない
・学校、会社に行きたくない
・人と話すのが面倒くさい
・やる気、元気が出ない
・何でもマイナス思考になりがち
・食欲がない
・集中力がなくなり、仕事や勉強が進まない
・疲れがとれない
・興味のあることや好きなことをやる気にならない
・からだが重く感じる
7つ以上当てはまった人は、5月病の可能性があります。
実は恐ろしい5月病、放っておくとどうなる?
「そのうち元に戻るだろう」と5月病を軽く見て放っておくのは危険。
なぜなら、5月病が長引くと「適応障害」から「うつ病」などの重い精神疾患に進行することがあるからです。
とくに、「がんばらなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」と自分を追い込みすぎてしまう人は、無意識のうちにストレスをため込みがち。
症状が慢性化すると、仕事や学業、人間関係など日常生活にも支障をきたすようになります。
小さな不調のうちに対処することで、悪化を防ぐことができます。
5月病かもしれないと思ったら、次に紹介するマインドセットを意識してみましょう。
5月病を乗り切るために大切なマインドセット
5月病の回復には、生活リズムの見直しが大前提。
まずは、睡眠・食事・運動の基本を整えましょう。
そのうえで、心の持ち方=マインドセットを意識することが、回復への近道になります。
「まぁいいか」を許す
新しい環境では、うまくいかないことや戸惑うことがあって当たり前です。
それにもかかわらず、「ちゃんとしなきゃ」「完璧にこなさなきゃ」と自分を追い詰めてしまうと、心がどんどん疲れてしまいます。
そんなときは、「まぁいいか」と自分を許してあげましょう。
完璧を目指すのではなく、今の自分にできる範囲でがんばることを自分に許してあげることが、回復の第一歩です。
ストレスと上手につきあう
毎日忙しく過ごすなかで、ストレスを完全になくすことは難しいでしょう。
ストレスをなくそうと努力することが、逆にストレスになってしまう人も。
ストレスはゼロにするものではなく、上手につきあっていくもの。
「ストレスがあるのは当然」「多少の不安があるのは普通」と受け入れるマインドを持つことで、気持ちが楽になります。
また、ゆっくりお風呂に入ったり、通勤通学時にいつもと違う道を歩いてみたり、自分なりのストレス発散法を取り入れることも大切。
心の疲れをため込まない工夫をしてみましょう。
無理せず心療内科を頼る
どうしてもつらいときや苦しいときは、自分ひとりで抱え込まないでください。
友人や家族に相談するのはもちろん、心療内科などの専門機関を頼るのも勇気ある一歩です。
早めに相談することで悪化を防ぎ、日常生活を取り戻すきっかけになります。
気になるときは一度受診して、心を楽にしてあげましょう。
メンタルの維持には漢方薬という選択肢も
心の不調に悩んでいる人は漢方薬の力を借りるのもひとつの方法です。
漢方薬は心療内科でも自然由来の医薬品として処方されており、心とからだの不調の根本改善を得意としています。
5月病の症状を改善するには、
・イライラや気分の落ち込みを改善する
・血流をよくして自律神経の乱れを整える
・消化・吸収機能を改善してからだの内側から心を元気にする
といった働きをもつ漢方薬を選びます。
<5月病の人におすすめの漢方薬>
・抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)
ストレスなどによる心の乱れを和らげ、イライラや抑うつといった神経症状、不眠などを改善します。
・柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
自律神経の乱れを整えることで、心とからだの状態を安定させ精神不安、動悸、不眠に働きかけます。
5月病かもと思ったら、早めのケアが大切。
早くケアをしたくても、忙しくてなかなか病院に行けない人や、ついつい自分のことを後回しにしてしまいがちな人は、オンラインで漢方薬のプロに相談するのもおすすめです。
「あんしん漢方」というサービスは、スマホひとつで漢方に精通した薬剤師に相談可能。
薬剤師がAI(人工知能)を活用し、たくさんある漢方薬の中から、あなたに最適な漢方薬を見極めてくれます。
大切な心とからだのため、安全・安心に漢方薬を始めるきっかけとして一度サイトをのぞいてみてください。
がんばりすぎないで、自分を守る選択を
心の疲れによる5月病は、放っておくと深刻な病気につながることもあります。
がんばりすぎて自分を追い込んでしまう前に、「まぁいいか」と自分を許してあげましょう。
ストレスと上手につきあいながら、小さな不調のうちに対処することで、心はきっと回復していきます。
<この記事の監修者>
横倉恒雄(よこくらつねお)医師
婦人科・内科・心療内科医
医学博士/医師。横倉クリニック・健康外来サロン(港区芝)院長。東京都済生会中央病院に日本初の「健康外来」を創設。故・日野原重明先生に師事。ストレスなどから不調を訴える患者さんにも常に寄り添った診療を心がけている。新刊本『今朝の院長の独り言』(青春出版社)はポジティブなメッセージに溢れていると話題に。クリニックで行われている講座も好評。
<漢方監修>
木村 英子(きむらえいこ)
あんしん漢方薬剤師
北里大学薬学部・東京大学大学院医学系研究科卒。臨床検査技師。
厚生労働省検疫所・病院にて公衆衛生・感染症現場を経て、インドアーユルヴェーダの権威ミーナクシ・アフジャ博士に師事。
対症療法ではなく体質を根本改善することの重要さを痛感し、西洋医学をベースに東洋医学からのアプローチを取り入れ、アロマやハーブを活用した情報発信を行う。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でもサポートを行っている。
●あんしん漢方(オンラインAI漢方):https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=211231g6sdf10029&utm_source=shindere&utm_medium=referral&utm_campaign=250429