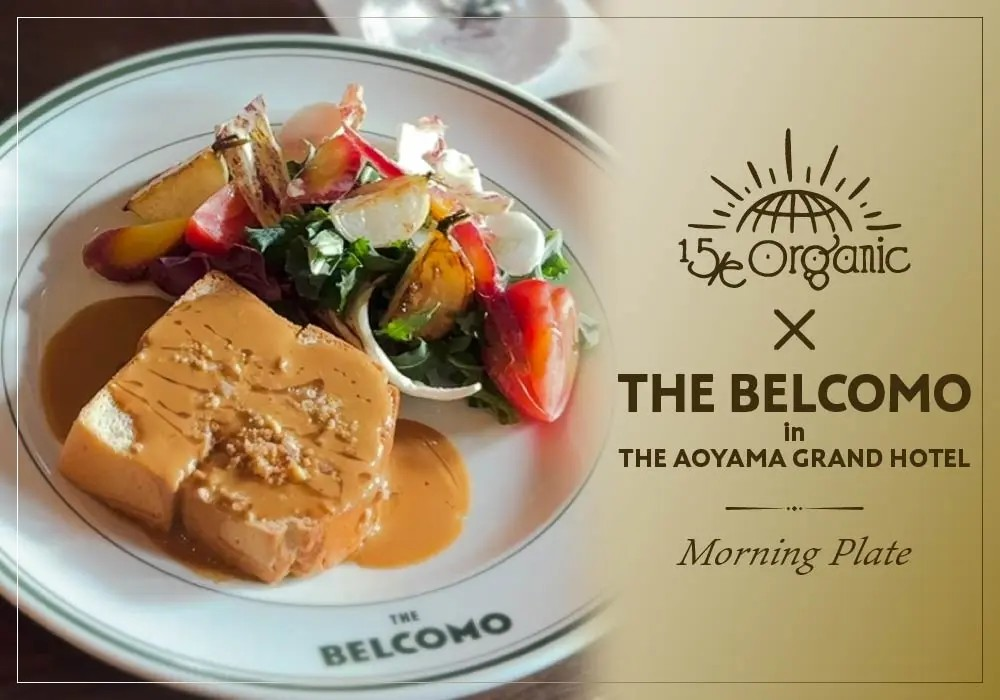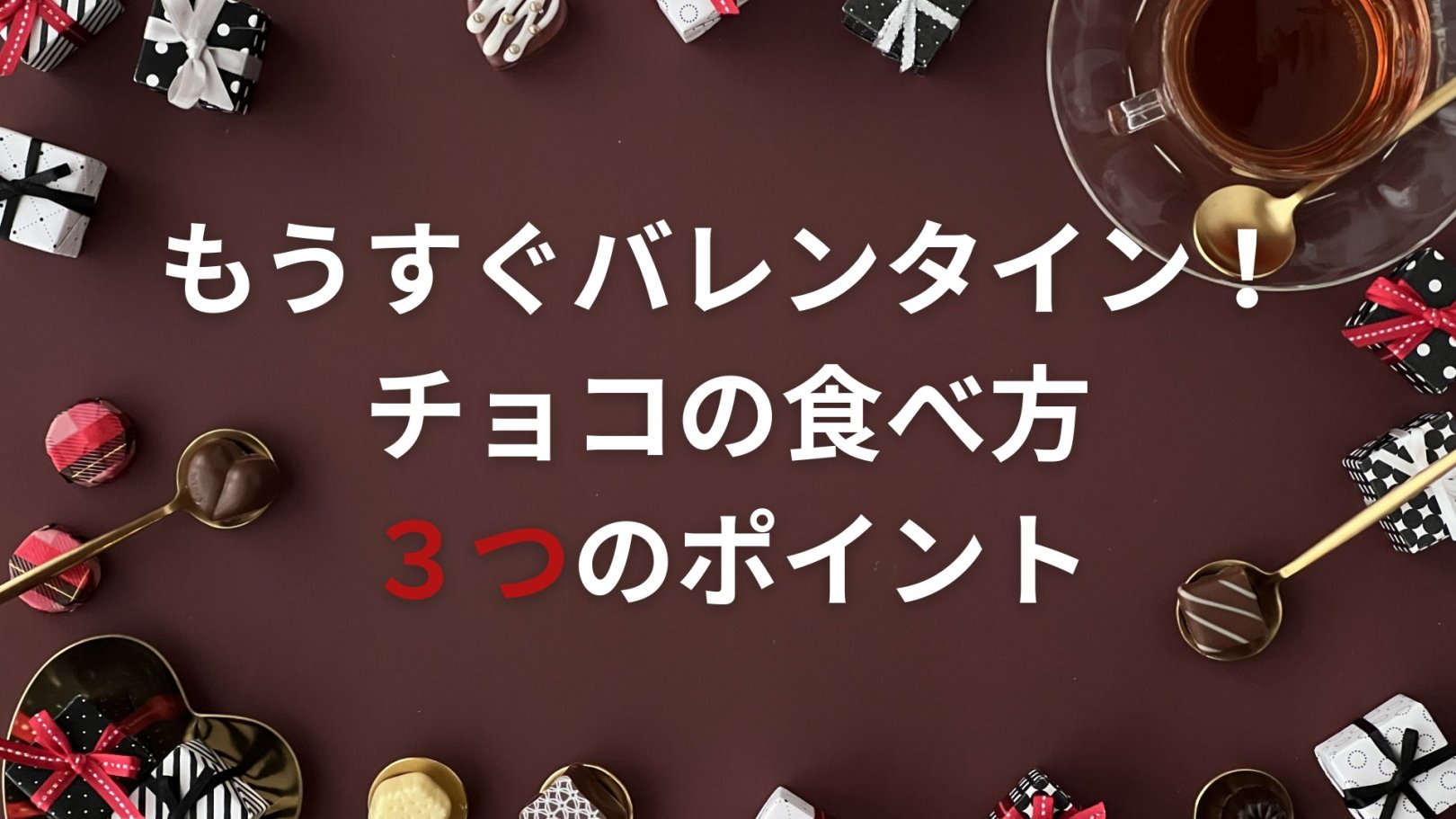月経にまつわる不調で婦人科に通う女性が、ここ10年で約3倍に増えている、という事実を知っていますか?「なぜそんなに増えたのか」その理由を知らずにいるのは、ちょっと危ないかもしれません。
とくに、仕事に家事にと忙しいキャリア世代の女性こそ、からだの不調を後回しにしがち。でも、無理を続けた先には、見過ごせないリスクが潜んでいるかもしれません。
今回は婦人科・心療内科医の横倉恒雄先生に、20~40代の女性にとくに増えている婦人科疾患とその背景、忙しい女性にこそ実践してほしいセルフケア法について伺いました。
増加する月経困難症(生理痛)の背景にある病気
――月経困難症などで婦人科に通院する女性が急増しているというデータがあります。2020年には、2000年比で約3倍に達している(※1)ようですが、実際に先生のクリニックでも増えている印象はありますか?
「月経困難症は増えていますね。私のクリニックでも、とても多いです。次いでPMS、生理不順、その他には膣炎なども多い傾向にあります」
――月経困難症とは何でしょうか?
「月経困難症は、いわゆる生理痛のことです。一言に“生理痛がある”と言っても、実はその原因はさまざまなんです。たとえば腹痛の場合、それが虫垂炎(盲腸)なのか、食あたりなのか、原因はいろいろ考えられますよね。それと同じで、生理痛というのは“結果”であって、何が原因なのかは人によって違うんです。
私のクリニックの患者さんのなかで、毎月生理痛があると答える女性は全体の約半数にのぼります。そして、“生理痛がつらい”という人の約3割に何らかの病気が隠れている印象があります。けっこう多いんですよ」
――生理痛が重い人の背景にはどのような病気が隠れているのでしょうか?
「子宮内膜症と子宮筋腫がもっとも多いです。子宮内膜症は、本来、子宮の内側にあるはずの子宮内膜の組織が、子宮の筋肉の中、卵巣内、子宮の裏側、骨盤の中など別の場所にできてしまう病気です。月経のたびに強い痛みが起こり癒着して、不妊の原因になることもあります。子宮筋腫は、子宮の筋肉にできる良性の腫瘍です。悪性化することはまれですが、筋腫が大きくなると、生理の量が増えたり、お腹の張り、貧血などの症状が出ることがあります」
早期発見や自分での見極めが難しい病気も
――それらの病気は、生理痛以外に見分けるポイントはあるのでしょうか?
「自分で気づくのは難しいです。たとえば子宮筋腫は、筋腫のできる場所によって症状の出方が異なるという特徴があります。子宮の内側にできた筋腫は出血や痛みといった症状が出やすく、比較的早く見つかります。一方で、子宮の外側にできた筋腫は症状が出にくいので自分ではまずわからないでしょう。かなり筋腫が大きくなっているのにまったく痛みがないという患者さんもときどきいます。
痛み止めを飲んで生理痛をやり過ごしてしまう人が多いですが、それで済ませてしまうと病気のサインを見逃してしまいます。痛みが強い場合は、婦人科を受診するか定期的に婦人科検診を受けてほしいです」
――婦人科検診はどのような検査なのでしょうか?
「婦人科検診とは、一般的には子宮頸がん検診をさすことが多いですね。子宮頸がん検診は、超音波と内診の両方をします。とくに内診では小さな異常や病気を見つけやすいんです。たとえば、子宮の裏側に子宮内膜症の病変ができている場合、超音波検査では確認できないこともあり、内診でわかることが多いです。
子宮頸がん検診はすべての女性に受けてもらいたいですが、生理痛が重い人はとくに受けるべきだと思いますよ」
「生理痛の重さ」と生活習慣の関係
――一方で、背景に病気が隠れていないのに生理痛が重い場合、原因はどこにあるのでしょうか?
「病気がないのに生理痛が重いのは『機能性月経困難症』といい、子宮が強く収縮してしまっている状態です。機能性月経困難症の場合、早い人では高校生くらいから生理痛が重くなります。
機能性月経困難症が増えている背景には、やはり生活習慣の影響がありますね。たとえば、薄着で骨盤を冷やすこと、長時間のデスクワークや車移動による運動不足などの影響は大きいです。座りっぱなしで血行が悪くなると、子宮が収縮しやすくなります。
そこに、“プロスタグランジン”というホルモンの影響も加わります。これは、陣痛促進剤にも使われる子宮収縮を促す物質です。プロスタグランジンが多く分泌されると、生理痛が強くなる……つまり、“冷え”と“血行不良”、そして“ホルモンの分泌”が合わさることで生理痛はひどくなるんですよ」
月経困難症の増加と「PMS」
――生理痛の重さには、生活習慣が関係しているのですね。ちなみに、PMS(月経前症候群)も、近年多くの女性が悩んでいると話題にのぼることが増えているようですが?
「そうですね。PMSも、クリニックで非常に多い相談のひとつです。一般的にはホルモンバランスの影響だと言われていますが、私は、そのベースに“ストレス”が大きく関係すると考えています。
私のクリニックでは、婦人科系の相談でも心理テストを実施していますが、ストレスを強く感じる人の方が明らかにPMSの症状が出やすい傾向にあるんですよ。
やはり、現代の女性の働き方、生活習慣、ストレスなどが、生理にまつわる不調を増加させている一因であることは否定できないでしょう」
PMSは漢方薬でからだのベースを整える
――ストレスや生活習慣の影響は、生理にまつわる不調に大きく影響を与えるんですね。ちなみに、PMSにはどのような治療法があるのでしょうか?
「PMSには、ピルと漢方薬を併用することが多いですね。まずはピルを飲んでホルモンの状態を一定にして、それでも症状が起こるかどうかを見ます。
たとえば、血行をよくする桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)、イライラや気分の落ち込みなどの精神的な症状が強くあらわれる患者さんには加味逍遙散(かみしょうようさん)や抑肝散(よくかんさん)などの漢方薬をよく処方します。冷えやむくみには、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)や、からだを温める生姜(しょうきょう)が入っている当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)という漢方薬もあります。心とからだのベースを整える意味で、漢方はとても有効なんです。
――漢方薬は自分でドラッグストアで買って試してもいいのでしょうか? 種類が多いので、選ぶのが難しいですよね。
「それはおすすめしません。漢方に関する知識があって、自分に合ったものを選べるならいいですが、自己判断で選ぶのは難しいんです。自分の体質や状態に合っていないと、副作用が出たり効果が得にくくなったりすることもあります。
あとは、薬や治療法に対する“信頼”も大事なんです。とりあえず飲めばいいわけではなく、『これは自分に合った薬だ』と信じられることや『専門家に選んでもらった』という安心感も、治療の一部だと思いますよ」
生理にまつわる不調にはセルフケアも大切
――最後に、読者の方が今日から実践できるセルフケアを教えてください。
「私がとくにやってほしいと思うセルフケアは主に3つあります。
まずひとつ目は、骨盤を動かす習慣をつけること。骨盤の血流をよくするための軽いエクササイズが効果的です。座りっぱなしの生活で骨盤まわりが固まっている人が多いですが、股関節をよく動かすことで、骨盤まわりの血行がよくなり、生理痛の緩和にもつながります。
ふたつ目は、骨盤を冷やさないこと。薄い下着や下半身を冷やすような服装も、できれば避けてほしいですね。骨盤が冷えると子宮の収縮が強まり、生理痛の悪化にもつながります。季節を問わず、下半身を温める工夫をしましょう。しっかり湯船に浸かって、からだの芯から温める習慣をつけることも大事です。
最後は、ストレスケアです。いろいろな方法があると思いますが「これをやればいい」という決まったものはありません。忙しくても簡単に取り入れられるおすすめの方法は、五感を使って“心地よさ”を味わうことです。五感を使う――というと、ピンとこない方もいるかもしれませんが、要は“自分が気持ちよく感じること”を生活のなかにどんどん取り入れるということ。
何か特別なことをする必要はありません。目的地までただ歩くのではなく空を見上げて風を感じてみる、食事は五感で味わって食べる、好きな香りに包まれる、ふかふかのタオルに触れる――どんな小さなことでもいいです。五感での感覚を大切にしながら自分に優しくすることで、からだも心もラクになっていきますよ」
心とからだの声に、もっと耳を傾けてみよう
横倉先生への取材を通して、月経困難症やPMSなどに悩む人が年々増えていることを実感しました。症状が重いのに痛み止めを飲むだけで我慢したりするのはご法度。他の病気が隠れている可能性があるので、婦人科での定期検診を受けることがとても大切です。
たとえ病気がなくても、ストレスや生活習慣の影響は、からだにしっかりあらわれているかもしれません。そんなときは、専門家に相談し、必要に応じて漢方薬なども上手に取り入れてみましょう。どこに相談すればいいか迷ったら、スマホひとつで漢方薬のプロに相談できる「あんしん漢方」のようなオンラインサービスも便利です。
今回、横倉先生がおすすめしてくれたセルフケアは、今からでも始められる方法ばかり。心とからだ、どちらの声も見逃さず、自分を大切にしていくことが、女性の健康を守ることにつながるでしょう。
参考文献
<この記事の監修者>
横倉恒雄(よこくらつねお)医師
婦人科・内科・心療内科医
医学博士/医師。横倉クリニック・健康外来サロン(港区芝)院長。東京都済生会中央病院に日本初の「健康外来」を開設。故・日野原重明先生に師事。病名がない不調を訴える患者さんにも常に寄り添った診療を心がけている。著書に『脳疲労に克つ』『心と体が軽くなる本物のダイエット』『今朝の院長の独り言』等がある。クリニックで行っている『しなやか更年期サロン』はオンライン参加もあり、外来では時間がなく聞けない質問等もゆっくり教えてもらえると好評。
<漢方監修>
木村 英子(きむらえいこ)
あんしん漢方薬剤師
北里大学薬学部・東京大学大学院医学系研究科卒。臨床検査技師。
厚生労働省検疫所・病院にて公衆衛生・感染症現場を経て、インドアーユルヴェーダの権威ミーナクシ・アフジャ博士に師事。
対症療法ではなく体質を根本改善することの重要さを痛感し、西洋医学をベースに東洋医学からのアプローチを取り入れ、アロマやハーブを活用した情報発信を行う。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でもサポートを行っている。