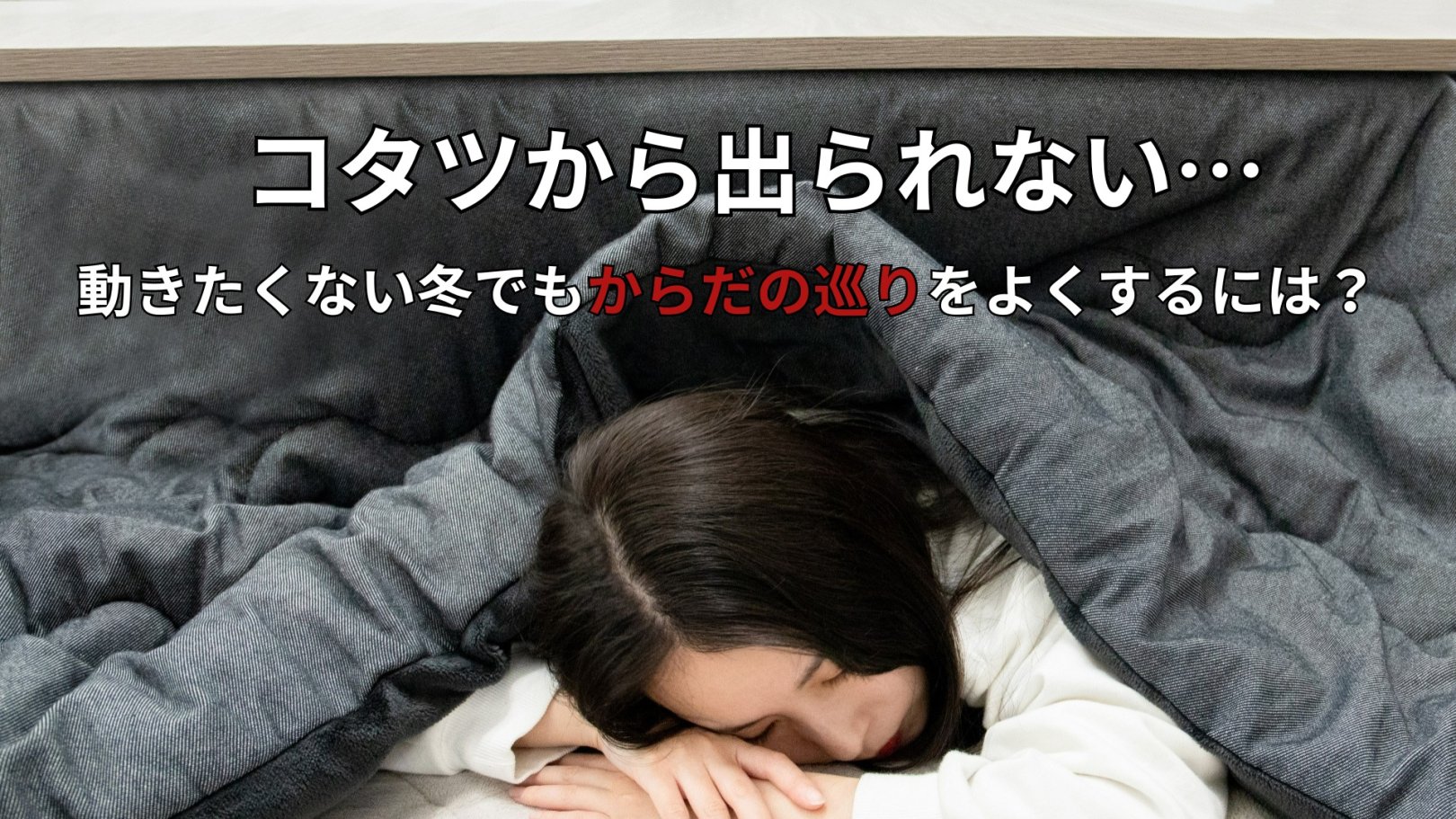「常にスマホを手放せない」「“ながら”スマホがやめられない」。
そんなスマホ依存しがちな日々を送るなかで、集中力の低下を感じていませんか?
それはもしかしたら「脳疲労」のサインかもしれません。
今回は、現代病ともいわれる脳疲労の基礎知識から、原因となる生活習慣、そして今日から始められるセルフケアまでくわしく解説します。
脳疲労とは?スマホ時代に増える“現代病”

脳疲労とは、脳に過度な負荷がかかり、本来の機能が低下した状態を指します。
人間の脳は、「浅く考える」「深く考える」「ぼんやり考える」という3つのモードのバランスをとりながら働いています。
ところが、四六時中スマホを眺めていると、大量の視覚情報が次々流れ込み、「浅く考える」モードばかりが酷使されてしまうのです。
その結果、「深く考える」「ぼんやり考える」モードは使われなくなってしまいます。
とくに情報の整理の役割を持つ「ぼんやり考える」という時間が失われると、脳は次第に疲弊していきます。
もし「集中力が続かない」「うっかりミスが増えた」「人との約束や予定を忘れることが多くなった」というサインに心当たりがあるなら、要注意です。
これらは単なる一時的な疲れではなく、脳が限界に近いことを示す危険信号かもしれません。放置するとうつ病や不安障害につながることもあるため、早めの対処が大切です。
脳疲労を引き起こす生活習慣

ここからは、脳疲労の原因になりうる3つの生活習慣についてチェックしていきましょう。
スマホ・ネット依存
用がなくても何となくスマホを触ってしまったり、SNSのタイムラインが気になって頻繁に見たりする習慣は、脳疲労の大きな原因です。
わずかなスキマ時間さえもスマホに費やすことで、脳が休まる暇のない状態に陥ってしまいます。
睡眠不足や不規則な生活
睡眠不足は、脳疲労を引き起こす代表的な要因です。
脳は睡眠中に日中に蓄積された老廃物を除去し、疲労を回復させます。しかし、生活が不規則になって睡眠が不足すると、この重要なメンテナンスが追いつかず、老廃物が脳内にたまりやすくなります。
また、寝不足は感情や理性を司る扁桃体や前頭葉などの働きを乱す原因に。その結果、ささいなことでもイライラしたり、不安や抑うつ的などの気分が強まったりしがちです。
ストレスや過度なマルチタスク
現代社会において、脳は常にストレスに晒されています。それに加え、複数の作業を同時にこなす「マルチタスク」も大きな負担となります。
本来、脳は複数のことを同時に処理するのが苦手です。スマホに意識が向くだけでも大きなストレスがかかり、作業を切り替えるたびにさらに脳の負担は増加します。
脳疲労を和らげるセルフケア習慣

ここからは、脳疲労を軽減するための4つのセルフケアについてご紹介します。
デジタルデトックス
デジタルデトックスとは、スマホやパソコンなどのデジタル機器から意識的に距離を置き、心身をリフレッシュさせる試みです。
まずは「食事中はスマホを触らない」など、無理のない範囲から始めて、続けることを意識しましょう。
また、スマホの代わりに楽しめることを見つけるのも効果的です。散歩や読書など、スマホから離れて集中できる趣味は立派なデジタルデトックスになります。
軽い運動と良質な睡眠
ウォーキングやヨガなどの、軽い有酸素運動は、脳の血流を促進し、脳の働きを高める効果が期待できます。短時間の運動でもいいので、習慣的に行うことが大切です。
また、質のよい睡眠をとることも脳疲労の回復には欠かせません。良質な睡眠のためには、就寝前のスマホの操作は控えましょう。
そして、入浴は就寝の2~3時間前に済ませるのが理想的です。
40度程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かると、からだの深部体温が上昇します。その後、深部体温が下降するタイミングでちょうど眠気がやってきて、スムーズな入眠につながります。
マインドフルネス
マインドフルネスとは、仏教の瞑想をベースにしたもので、「今この瞬間」に意識を集中させる心のトレーニングです。
ストレスや不安を軽減したり、睡眠の質を向上させたりする可能性があるとして、科学的な研究も進んでいます。
マインドフルネスの基本的なやり方
1. 静かな場所に座り、背筋を伸ばす
2. 目を閉じ、呼吸に意識を向ける
3. 鼻から息を吸い、口からゆっくり吐く
4. 呼吸の流れに意識を集中する
雑念が浮かんだときは、無理に消そうとせず、考えが浮かんだことを客観的に受け止め、意識を少しずつ呼吸に向けましょう。
漢方薬の活用
脳疲労やストレスによる不調を和らげるには、漢方薬もおすすめです。漢方薬は、心身のバランスを整えることで、不調の根本改善をめざします。
脳疲労を緩和するには、「血流をよくして脳に酸素や栄養を届ける」「自律神経のバランスを整えストレスを緩和する」「ホルモンバランスの乱れを整える」「胃腸機能をよくして消化を助ける」といった効果が期待できる生薬を含む漢方薬を選びましょう。
<脳疲労を緩和する漢方薬>
・人参養栄湯(にんじんようえいとう)
胃腸の機能を高め、エネルギーと栄養を補い、食欲不振、疲労・倦怠感、不眠などの精神症状を改善します。
・加味逍遙散(かみしょうようさん)
上半身にこもった余分な熱を冷ますことで、イライラや不安などの精神神経症状、ほてり、のぼせを緩和します。
漢方薬は体質との相性が重要です。医師や薬剤師に相談し、ご自身に適切な漢方薬を選んでもらいましょう。
最近では、オンラインで気軽に相談できる「あんしん漢方」のような漢方薬サービスも登場しています。
あんしん漢方は、体質診断、漢方薬の提案、アフターフォローまですべてインターネットを通じて完結できるのが魅力です。通院の時間がとれない忙しい方や、感染症リスクが気になる方にも向いています。
セルフケアを駆使して脳をいたわる
スマホ依存は脳疲労の大きな原因となります。
今回ご紹介したデジタルデトックスや適切な運動と良質な睡眠、マインドフルネスなどを生活にとり入れて、意識的に脳の負担を和らげてあげましょう。
そして継続的にセルフケアを実践することが、健やかな毎日を送るための第一歩です。
<この記事の監修者>
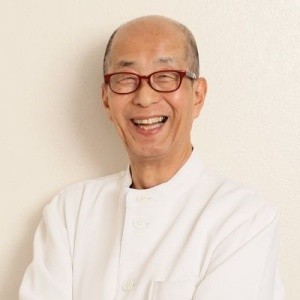
横倉恒雄(よこくらつねお)医師
婦人科・内科・心療内科医
医学博士/医師。横倉クリニック・健康外来サロン(港区芝)院長。東京都済生会中央病院に日本初の「健康外来」を開設。故・日野原重明先生に師事。病名がない不調を訴える患者さんにも常に寄り添った診療を心がけている。著書に『脳疲労に克つ』『心と体が軽くなる本物のダイエット』『今朝の院長の独り言』等がある。クリニックで行っている『しなやか更年期サロン』はオンライン参加もあり、外来では時間がなく聞けない質問等もゆっくり教えてもらえると好評。
<漢方監修>

木村 英子(きむらえいこ)
あんしん漢方薬剤師
北里大学薬学部・東京大学大学院医学系研究科卒。臨床検査技師。
厚生労働省検疫所・病院にて公衆衛生・感染症現場を経て、インドアーユルヴェーダの権威ミーナクシ・アフジャ博士に師事。
対症療法ではなく体質を根本改善することの重要さを痛感し、西洋医学をベースに東洋医学からのアプローチを取り入れ、アロマやハーブを活用した情報発信を行う。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でもサポートを行っている。